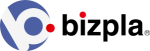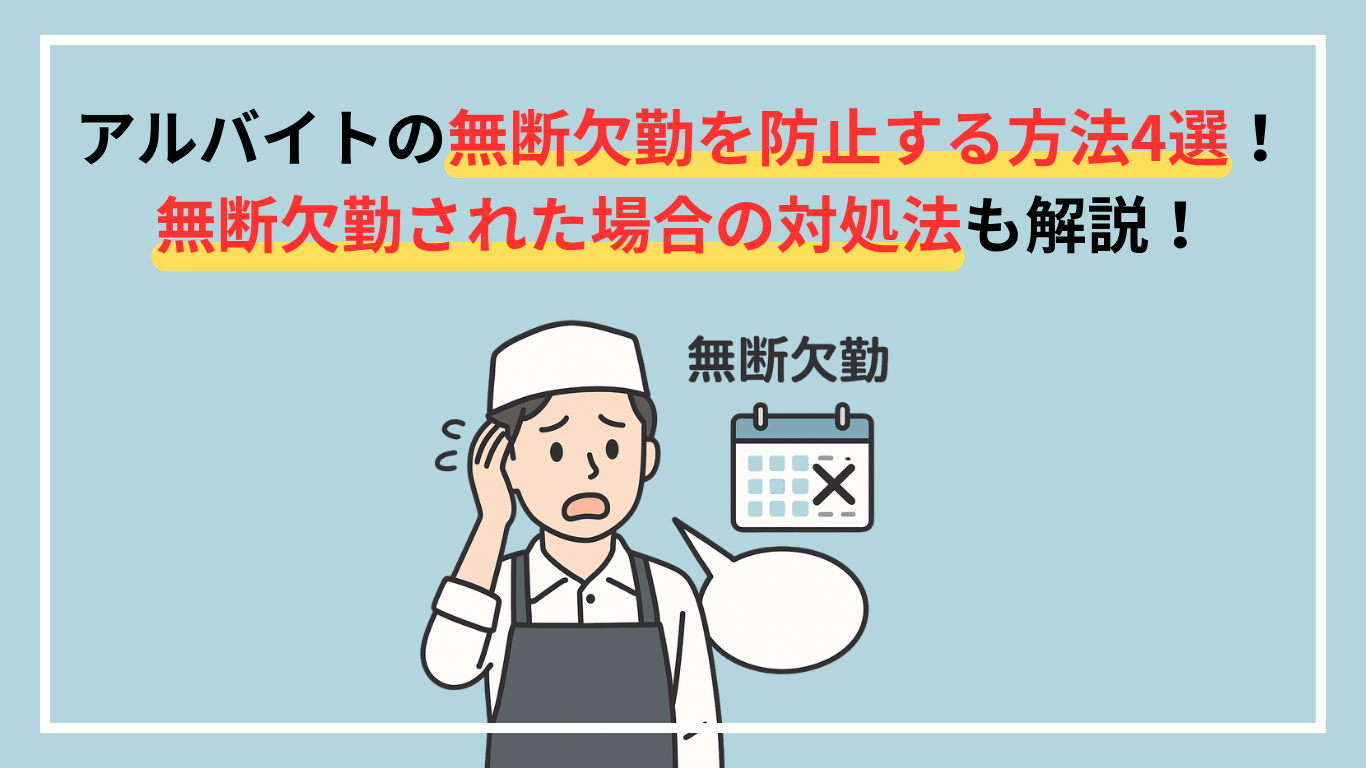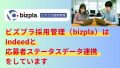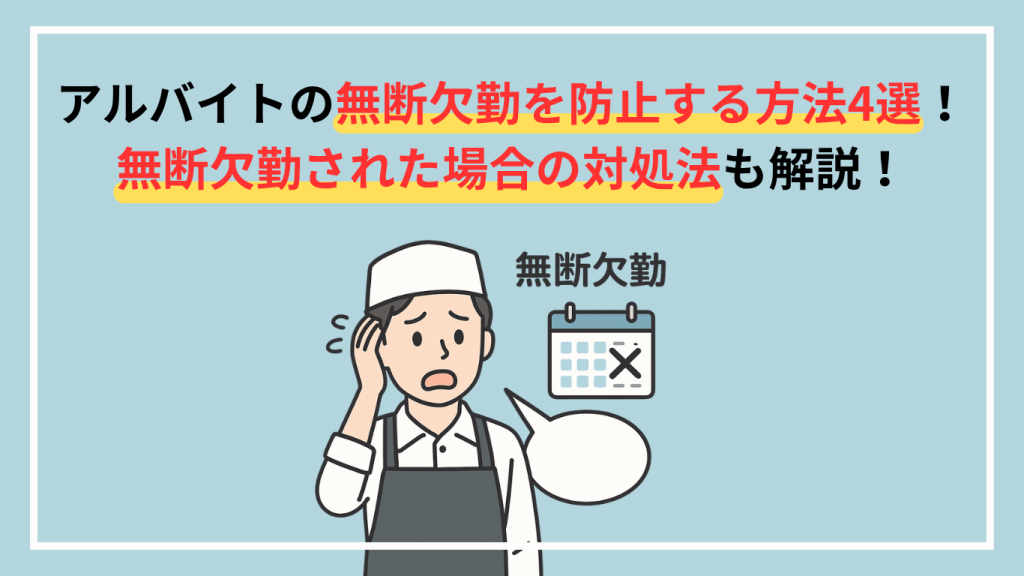
アルバイトスタッフの無断欠勤は、現場に大きな影響を及ぼすこともあります。
とはいえ、日頃のちょっとした工夫で未然に防げるケースも少なくありません。
この記事では、無断欠勤を防ぐための4つの方法と、実際に発生してしまった場合の適切な対応について、わかりやすくご紹介します。スタッフが安心して働ける環境づくりのヒントとして、ぜひご活用ください。
アルバイトが無断欠勤をしたらまずやるべきこと
当日になってアルバイトが出勤してこないことは、珍しいことではありません。アルバイトやパートの無断欠勤が発覚しても慌てるのではなく、まずやるべきことに着手しましょう。
アルバイトに連絡をする
まずは、無断欠勤したアルバイト本人に連絡を試みましょう。連絡手段は、電話やメール、メッセージアプリなど、複数の方法を使っても問題ありません。連絡をする際は、以下の点を確認します。
・無断欠勤の理由
・今後の出勤意志
寝坊やシフトの勘違いなど、やむを得ない理由であれば、今後の対策を話し合います。しかし、連絡が取れない場合や今後も出勤する意志がないと伝えられた場合は、退職手続きを進める必要があります。
会社からの連絡に応じない場合は、同僚のアルバイトに連絡して、理由だけでも聞いてもらいましょう。
欠員を埋める
次に、欠員が出た状態では営業に支障を来す場合は、他のアルバイトや社員にヘルプを依頼したり、スキマバイトで人員を募集したりしましょう。
人員不足による営業への影響を最小限に抑えるためには、欠員が出た時点で迅速に人員を確保することが重要です。
緊急連絡先に連絡する
本人と連絡が取れない場合は、アルバイト契約時に提出された緊急連絡先(家族や親族など)に連絡します。
すぐに緊急連絡先に連絡をするべき理由は、本人が無事かどうか確認をするためです。事件や事故に巻き込まれている可能性もあるので、連絡が取れないからといって、無断欠勤をしたと会社側で勝手に判断してはなりません。
緊急連絡先にも連絡がつかない場合は、自宅訪問するしかありませんが、本人が嫌がることが考えられるため、慎重な判断が必要です。
緊急性が高い場合や、勤務態度が良好で事件や事故に巻き込まれた可能性があると判断した場合に限って、訪問したほうが良いでしょう。
無断欠勤後もしばらく連絡が取れない場合の対処法
無断欠勤をされてからしばらく経ってもアルバイトやパートと連絡が取れないことがあります。
もう自社には関係のない従業員だからと放置するのは良くありません。ここからは、従業員としばらく連絡が取れず、明らかに出勤する意思がない場合に会社がやるべきことを紹介します。
内容証明郵便を送る
無断欠勤した翌日以降も連絡がない場合は、以下のような内容を記載した内容証明郵便を送ります。
・出勤日
・連絡がない場合の対応(自己都合退職など)
・返答期限
内容証明郵便は、配達証明付きで送付することで、相手が受け取った事実も証明できます。また、内容証明郵便を送ることで、相手に心理的なプレッシャーを与え、連絡を促す効果も期待できます。
備品回収の連絡をする
続いて、携帯電話、パソコン、タブレット、鍵、制服など、貸与品の回収を行います。連絡が取れない場合は、返却依頼を理由に留守番電話やメールで記録を残しましょう。
連絡時には、以下の内容を伝えます。
・貸与物の内容
・未返却の事実
・返却期限
・返却方法
・返却がない場合の法的措置
個人情報を含む備品を返却していない場合、企業に重大な損害をもたらす可能性があります。返却を強く求めましょう。
退職や解雇手続きを行う
次に退職や解雇手続きを進めますが、安易に行わないように注意が必要です。なぜなら、後日アルバイトから不当解雇として訴えられる可能性ややむを得ない事情があることを考慮する必要があるからです。
また、並行して、社会保険と雇用保険の喪失手続きも進めます。
| 社会保険の喪失手続き | ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を、退職日の翌日から5日以内に日本年金機構へ提出する ・アルバイトの被扶養者がいる場合は、被扶養者異動届も提出する |
| 雇用保険の喪失手続き | ・雇用保険被保険者資格喪失届を、退職日の翌日から10日以内にハローワークへ提出します。 ・離職証明書を作成し、アルバイトへ交付(アルバイトから希望があった場合) |
無断欠勤して連絡が取れずに解雇した場合でも、給与の支払いは必要です。未払い賃金がないよう、給与計算を行いましょう。
そして、解雇予告手当の支払いが必要になる場合もあります。また、解雇理由証明書の発行を求められた場合は、速やかに発行しなければなりません。
解雇理由証明書を求められた場合は、解雇の理由、解雇日、解雇の根拠となる就業規則の条項などを記載して発行しましょう。
アルバイトへの損害賠償請求は難しい
アルバイトのバックレにより会社が損失を被った場合、損害賠償請求は法的に可能です。しかし、具体的な損失額を明確に立証する必要があり、現実的には損害賠償請求をするのは、非常に困難です。
例えば、アルバイト1人の欠勤で営業ができなかったことが直接的な損害として認められる可能性は低いでしょう。なぜなら、キッチン担当者1人が欠勤しただけで開店できない状況は、会社側の体制に問題があると判断されるリスクがあるからです。
また、損害賠償請求には、時間と労力がかかり、訴訟費用や弁護士費用も必要です。費用を掛けた割に回収できる金額が少ない傾向があるので、推奨できません。
そもそもアルバイトの無断欠勤を防止する方法
無断欠勤をされてから焦るのではなく、そのような事態を未然に防ぐことが重要です。ここでは、アルバイトの無断欠勤を防止する方法を紹介します。
就業規則に無断欠勤について記載した上で周知する
就業規則には、無断欠勤した場合の規則や対応方法について以下の内容を記載しておきましょう。
・無断欠勤が起こった場合の対応手順
・無断欠勤に対する罰則(罰金、厳重注意など)
・懲戒解雇の可能性
ただし、罰則は、無断欠勤の程度や回数など、客観的に合理的な理由と社会的相当性がある場合にのみ適用できる点に注意が必要です。また、いきなり懲戒解雇などの重い処分を下すのではなく、まずは注意や指導を行い、改善が見られない場合に段階的に処分を重くしていくことを推奨します。
そして、就業規則の内容について、雇用契約時や日頃から周知する必要があります。
日頃から無断欠勤のリスクや処遇について周知しておくことで、アルバイトの意識を高めることが可能です。
アルバイトとのコミュニケーションを強化する
アルバイトが不満を感じて無断欠勤をさせないためには、コミュニケーションを強化して信頼関係を構築することが重要です。
アルバイトとの定期的なコミュニケーションの機会を設け、アルバイトとの信頼関係を築きましょう。具体的には、以下の方法が有効です。
・日常業務中の声かけ
・定期的なミーティングの実施
・不満や希望のヒアリング
・業務への感謝を伝える
・アルバイトが不満を言いやすい環境を作る
業務中のちょっとした声かけは、アルバイトとの距離を縮める上で非常に有効です。「お疲れ様」「何か困ったことはない?」など、相手を気遣う言葉をかけることで、親近感が生まれ、信頼関係構築につながります。
日頃からコミュニケーションを取っておくことで、不満や悩みを抱えたアルバイトが無断欠勤をすることを防止できます。
無断欠勤には毅然とした態度で対応する
無断欠勤が発生した場合は、就業規則を遵守し、毅然とした態度で対応します。規則を反故にしたり、曖昧な状況を作ったりしないようにしましょう。
会社に落ち度がない場合に安易に妥協した態度を見せると、他のアルバイトから無断欠勤される可能性が高くなります。
無断欠勤するような人を採用しない
採用時に、無断欠勤する傾向がある人物を見抜くことも重要です。以下の特徴を持つ人物は、採用後に無断欠勤をする可能性があるので注意しましょう。
・人間関係に悩んでいる
・仕事内容や会社に不満がある
・大きな失敗のトラウマがある
・寝坊が多い(朝に弱い)
・仕事を軽視する行動が見られる
人間関係に悩んでいる人は、職場に適応しにくいため、ストレスや不安を抱えやすい傾向があります。
特に、過去に人間関係でトラブルを経験している場合、新しい職場でも同様の問題が起こることを恐れ、出勤を避ける可能性があります。
また、仕事を軽視する行動が見られる人は、「アルバイトだから」「どうせ誰かがカバーしてくれる」といった考えを持ちやすく、安易に無断欠勤を選ぶ可能性があるので注意しましょう。
面接時にこれらの傾向に気づいた場合は、採用を見送ることを推奨します。採用後になって気づいた場合でも注意深く見守ることで無断欠勤を避けられるかもしれません。
ビズプラ採用管理で採用業務の負担を減らすことが重要
無断欠勤を防止するためにアルバイトとコミュニケーションを取りたいけど、採用業務の負担が大きくてできない方は、ビズプラ採用管理により採用業務の負担を軽減できます。

ビズプラ採用管理なら100以上の求人媒体からの応募者情報を高速で取り込み可能です。
さらに、採用チャットボットのスクリーニング機能により、面接予約とお断りの連絡の振り分けを自動でできます。
採用業務の負担軽減により、アルバイトの定着率アップの施策に時間を注ぐことが可能です。
ビズプラ採用管理には、他にも以下のようなメリットがあります。
IndeedとIndeed PLUSに連携している採用管理システム(ATS)
SMSやLINEで素早く応募者に返信
採用のお役立ち情報をお届け
月額80,000円~の安心プライス
電話とメールでしっかりサポート
「でも、うちの会社に合うかな・・・」なんて迷っている方、大丈夫です!
まずは無料でオンライン相談してみませんか?